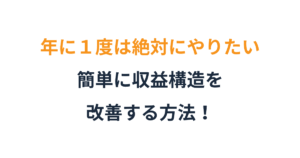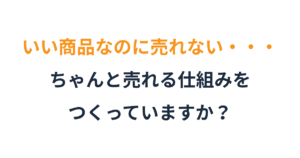評価制度がなくても ”納得感のある給与” をつくる方法

株式会社のびしろ経営
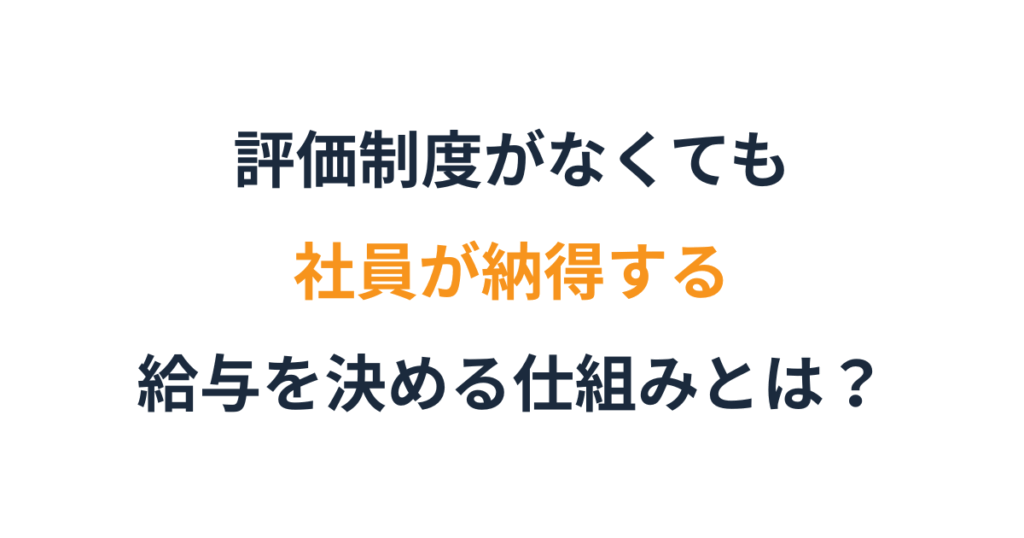
「うちは評価制度が整っていないから、給与に不満がでやすくて…」
「人件費の限界はある、でも、社員に納得してほしい」
そんな悩みを抱える中小企業の社長は多いです。
実は、きちんと制度がなくても ”納得感のある給与設計” は可能です。
カギになるのは、「見える化」「説明力」「仕組み」の3つです。
今回は、評価制度がなくても社員の納得を得られる方法をお伝えします。
「納得感のある給与」とは何か?
納得感とは、必ずしも「金額の多さ」ではありません。
むしろ、次のようなことが整っているときに、人は納得します。
・なぜその金額なのか説明がある
・他人との比較で不公平感がない
・自分が何をすれば上がるのか明確である
つまり、「感情的に納得できる理由」があることが大切です。
評価制度がなくても納得を生む3つの方法
①「給与の基準」を言葉で説明できるようにする
まずは、社長の中にある「感覚的な基準」を言語化します。
例えば、
・担当している業務の範囲・責任の重さ
・チームへの貢献度
・売上・利益への影響
・勤務年数や成長度
このような要素をもとに、「この人はなぜこの給与なのか?」を説明できる状態にしておきましょう。
社内で共有する場合は、一覧表にしておくと効果的です。
②「できること」と「もらっている金額」を対応づける
社員が納得できない一番の理由は、「何をしたら上がるのかが見えない」ことです。
そこで、スキルや役割に応じて「できることシート」をつくりましょう。
あくまで例えばですが、
給与ランク できることの目安
Aランク(月30万円) 新人指導ができる/主要顧客対応を1人で完結できる
Bランク(月25万円) 月次業務を1人で回せる/報告・連絡が安定している
Cランク(月22万円) 基本的な業務を自力で遂行できる
このように、「給与=スキルの対価」という構図が明確になると、
社員は、「どう成長すれば、どう上がるのか」が分かるようになります。
③昇給のルールを決めておく
例えば、
・毎年1回、見直す
・スキル評価に基づいて昇給幅を決める
・チーム貢献度を加味する
など、「どうすれば上がるのか」「どんなときは据え置きか」を明示するだけで、給与への納得感は格段にあがります。
のびしろ経営の支援事例
ある10名規模の会社では、評価制度がなく「なんとなく」で給与を決めていました。
そのため、若手から「なぜ先輩よりも自分の方が働いているのに給与が低いのか?」と不満が出ました。
そこで、
・社長の「感覚的な基準」をヒアリングし、5段階のスキルマップを作成
・昇給基準を「スキル習得+チーム貢献度」で整理
・半年に1回、面談で説明することをルール化
これにより、制度らしい制度はないものの、「納得できる給与」となりました
制度も大事ですが、「社長の言葉」が人を動かす
評価制度が整っていないからといって、給与が曖昧でいいわけではありません。
社員が気にしているのは、「自分のことを見てくれているのか?」「どうすれば成長できるのか?」です。
のびしろ経営では、スキル表、給与設計、面談など「感覚を制度に変える」お手伝いをしています。