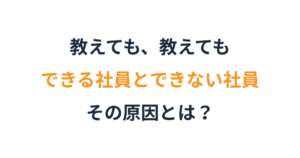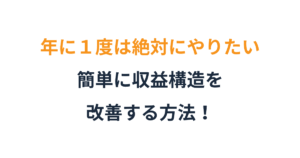「もう値下げしない」と決めるために、やるべきこと

株式会社のびしろ経営
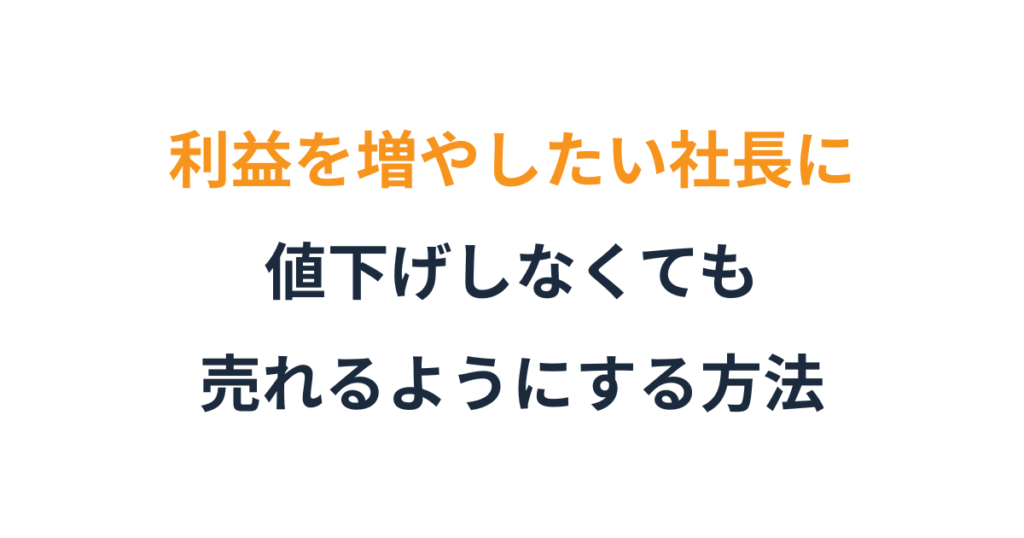
「値段を下げれば売れる…でも利益が出ない」
「競合に合わせて価格を下げざるを得ない」
「お客様から ”高い” と言われるのが怖い」
多くの中小企業が抱える悩みのひとつが、”価格のジレンマ” です。
でも、安売りで消耗する経営を続けていては、
事業は利益体質にならず、やがて自分もチームも疲弊してしまいます。
では、「もう値下げしない」と覚悟するために、何が必要なのでしょうか?
「値下げしなくても売れる会社」の共通点
値下げをせずに、売上を伸ばしている会社には、次のような共通点があります。
・価格ではなく「価値」で勝負している
・お客様が「比べる対象」が明確にズレている
・価格の背景にあるストーリーを語っている
つまり、価格ではなく、「納得の理由」を提供しているのです。
値下げをやめるための「3つの準備」
①提供価値を「言語化」する
「高品質」「丁寧な対応」「こだわりの素材」…だけでは伝わりません。
具体的にどんな人に、どんなメリットがあるかを明文化しましょう。
例)
×「こだわりの無添加素材使用」
〇「毎日子供に食べさせるお母さんが、安心して使える ”7つの無添加” 設計」
「誰の悩みをどう解決するか」が語れれば、値段ではなく「納得」で買ってもらえます。
②比較されないポジションをつくる
競合と同じ土俵にいる限り、価格で比較されます。
・ターゲットを変える
・販売方法や提供体験を変える
・セット販売や定額制にする
など、土俵ごと変える工夫が必要です。
例)
おなじ写真館でも「お宮参り写真を撮る店」ではなく、
「祖父母と3世代で残す、人生最初の家族写真」に変えれば、比較軸が変わります。
③自信を持って価格を伝える「マインド」をつくる
実は、値下げが続く背景には「価格を堂々と言えない社長の不安」があることも多いです。
・なぜこの価格なのか?
・それが、どうお客様の未来を変えるのか?
これを言葉にして、自分が一番納得している状態をつくりましょう。
値付けの自信は、「自社への信頼」の鏡です。
のびしろ経営の支援事例
A社では、
「安くて早い」が強みだったため、価格競争に巻き込まれて赤字に。
そこで、商品の価値を再定義し、
・お客様の導入支援まで一貫サポートする体制
・導入後の効果測定・フォロー付き提案
・専用パッケージ設計(比較できない設計)
に切り替えたことで、単価が1.5倍に上がりながらも受注が増加しました。
値段で迷う経営から「価値で選ばれる経営」へ
「値段を下げるか、売れないか」ではなく、
「値段を保ったまま、”欲しい” と言われるか」が、これからの経営に必要な視点です。
価格は「戦略」であり、「哲学」でもあります。
のびしろ経営では、価値の言語化、商品の再設計、価格設定の根拠づくりなど、利益が出る価格戦略の構築を支援しています。