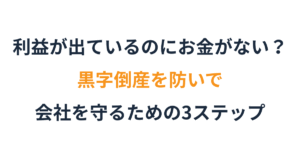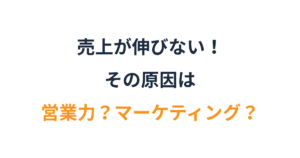社員が ”言われたことしかやならい” 理由と、変える方法

株式会社のびしろ経営
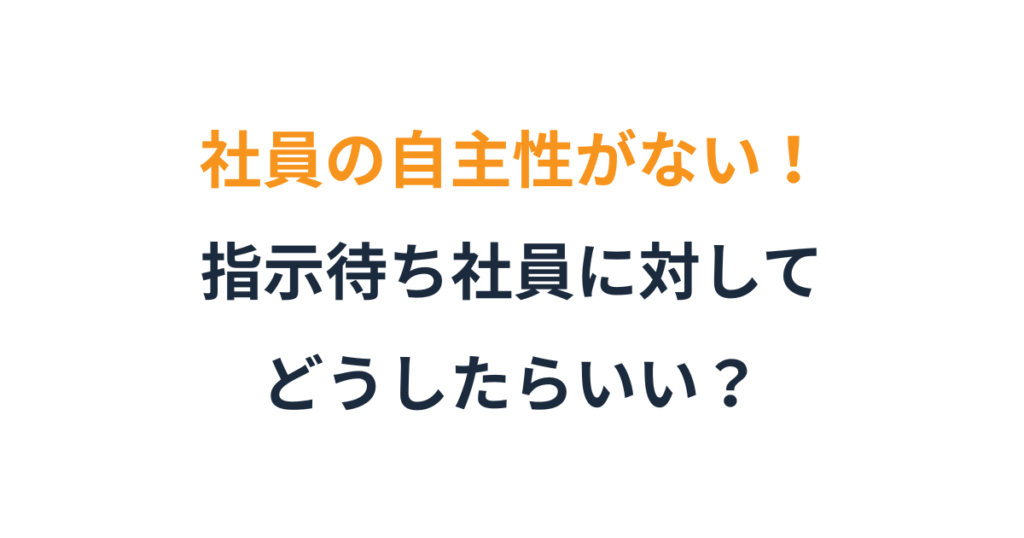
「自分から動かない」
「指示しないとやってくれない」
「もっと考えて動いてほしいのに…」
これは多くの社長が抱える ”人に関する典型的な悩み” です。
けれど、よく観察してみると、
社員の主体性が低いのではなく、「主体性が育たない環境」になっていることがほとんどです。
今回は、「なぜ指示待ち人間が生まれるのか?」という構造と、今日からできる改善のヒントをお伝えします。
「言われたことしかしない人」が生まれる3つの理由
①判断軸が共有されていない
例えば、
「このお客様には、どこまでやっていいのか?」
「この対応は、今やるべきか?」など
判断基準が見えないと、人は「動けない」のです。
だからこそ、「動かない」のではなく、「動けない」のかも知れません。
②失敗したときに「責任を問われる」空気がある
過去に「自分で判断して動いたら怒られた」「失敗して叱責された」という体験があると、人は安全策として「言われたことだけをやる」ようになります。
結果として、リスクをとらず、指示待ちの姿勢が習慣化してしまいます。
③「やるべきこと」が見えていない
やることが曖昧、優先順位が見えない、期待されるアウトプットが不明確…。
そんな状態では、人は当然「受け身」になります。
社員が「自ら動くようになる」ための3つの打ち手
打ち手① 判断軸を共有する
「こういうときは、こう考える」
「会社として大切にしているのは〇〇」といった
”価値観ベース” の行動判断基準を日ごろから伝えるようにします。
具体的な例を使いながら対話すると、理解が進みやすくなります。
打ち手② 安心して ”試せる場” をつくる
「動いてみた」「やってみた」に対しては、
結果が上手くいかなくても、まず「承認する姿勢」を持つこと。
試行錯誤を肯定することで、行動量が増えます。
フィードバックは「事後に丁寧に」が鉄則です。
打ち手③ 役割と成果の ”見える化” をする
・誰が、何を、いつまでに
・期待される成果物(例:集計レポート、顧客対応件数など)
・なぜそれをするのか(背景・目的)
これらを明示するだけで、社員は「自分の仕事の意味」をつかみやすくなり、自然と能動性が高まります。
社員の行動は、「社長の設計」で変えられる
社員が「やらない人」ではなく、「やれない環境」に置かれているだけかもしれません。
だからこそ、
「指示」ではなく、「判断基準と仕組み」を渡すこと。
これが、行動を変え、成果を変え、組織全体の動きを変える第一歩です。
のびしろ経営では、役割設計・行動基準の言語化・評価制度設計など、「人が育つ仕組み」の構築をお手伝いしています。
「人が動かない」と悩んだときこそ、仕組みづくりのチャンスかもしれません。