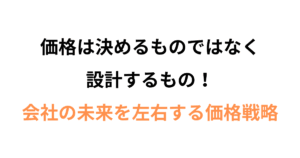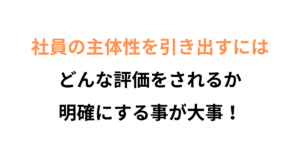社員が動かないのは、能力より ”構造” の問題かもしれない

株式会社のびしろ経営
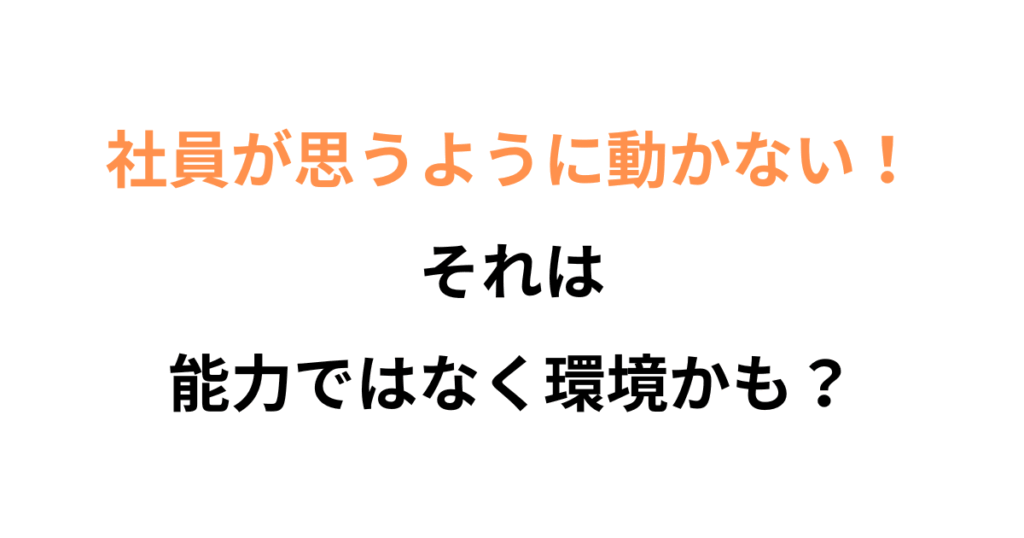
「指示を出しても社員が自分で考えない」
「何度言っても動かない。やる気がないのか…?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
でも、実は社員の「動かない原因」は、能力や意欲ではなく「会社の構造」にあることが多いのです。
今回は、現場が自発的に動かない理由と、それを改善するための組織構造の見直しポイントをお伝えします。
社員が動かないのは、やる気のせいではない?
社員が動かない=「やる気がない」と思いがちですが、
よく観察すると、「何をすればいいか分からない」「判断できない」という状態に陥っているだけのことも多いものです。
その背景にあるのは、次のような「構造的な問題」です。
・指示が曖昧で、自分の役割が不明確
→「誰が、何を、いつまでに、どうやるか」が整理されていない
・判断基準が共有されていない
→「こういうときは、こう判断する」というルールがないため、動けない
・行動しても評価されない・変化が起きない
→動いても意味がないと感じると、人は動かなくなる
解決のカギは「構造づくり」
では、どうすれば社員が「動ける組織」になるのでしょうか?
ポイントは、社長の指示や期待に頼るのではなく、社員が自走できる「構造」を整えることです。
構造づくりの3つのポイント
①「役割と目標」を明確にする
まずは、ポジションごとの役割・責任範囲を整理します。
「売上をつくる」「現場を回す」「数字をまとめる」など、 ”何を期待されているか” をはっきりさせることで、社員の行動が変わります。
あわせて、個人やチームごとに「目標数字」も明示しましょう。
数字は動きの「基準」になります。
②「判断基準」を共有する
現場で社員が迷わず動くには、判断ルール(行動原則)が必要です。
例えば、
・迷ったらお客様の立場で考える
・採算が合わなければ上司に相談
・不安なときは必ず確認をとる
こうした共通のルールがあるだけで、判断のスピードと精度が上がります。
③「動いた結果が見える・評価される仕組み」をつくる
社員が頑張っても、なにも変わらなければ、やがて動かなくなります。
・数字や成果が見える「見える化シート」
・月次のフィードバックミーティング
・小さな改善でも表彰・コメントをする文化
こうした工夫で、「動けば何かが起きる」と実感できる環境を整えましょう
社長の「がんばり」では限界がある
「社員を育てたい」「自分が現場に入らなくても会社が回るようにしたい」
その実現のためには、社長の声掛けより、社員が動く「仕組み」を設計することが不可欠です。
人の問題を「人のせい」にしない
それが、会社ののびしろを広げる経営の視点です。
社員が育つのは「構造のおかげ」
人材育成も、行動変容も、気合では続きません。
仕組みと構造によって、「育つのが当たり前」な組織をつくっていきましょう。
のびしろ経営では、役割設計・行動ルール・目標管理など、「動ける組織」の土台づくりを伴走支援しています。