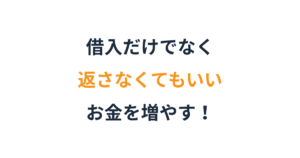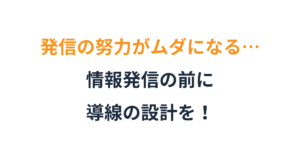”社員が言うことを聞かない”は社長の伝え方で9割変わる

株式会社のびしろ経営
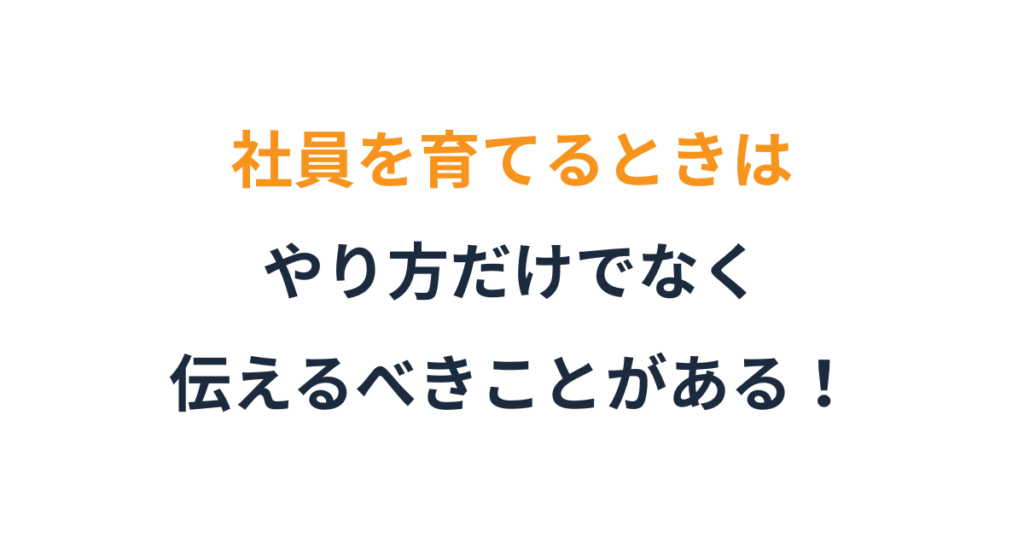
「何度言っても、同じミスをする」
「指示を出しても、やり切らない」
「結局、自分が動いた方が早い」
そんなふうに感じるとき、
「社員の能力」や「やる気」のせいにしたくなる気持ちは分かります。
しかし、現場でよく見られるのは、
「伝え方」や「伝わり方」がズレているケースです。
今回は、社員の行動を変えるために、社長ができる「伝え方の改善ポイント」を3つご紹介します。
「指示」ではなく「目的」を伝える
社長がつい、言ってしまうのは…
・「この資料を〇日までにつくって」
・「〇〇さんに電話しておいて」
・「ここ直しておいて」
これは単なる「作業指示」なので、社員は「言われたとおりにやればいい」と考えます。
結果、自分で考えない、ズレた成果物になる、状況が変わっても対応しないといった現象がおきます。
(改善ポイント)
・「なぜそれをやるのか?」という背景(目的)をセットで伝える
・「何を達成したいのか?」という成果のイメージを共有する
指示ではなく、「目的と着地点」が共有されると、社員は自分で判断し、能動的に動くようになります。
「分かっているだろう」は危険
社長がよく陥るのが、
「これくらい言わなくても分かるはず」
「これまで何回も言ってきたよね」という期待(ワナ)
でも社員は、
「また何か怒られた…けど、何が悪かったのか分からない」
「言われたことはやったのに…、なぜ不満なのか分からない」
これは、「伝えたつもり」と「伝わったつもり」のズレです。
(改善ポイント)
・あいまいな表現(たとえば「ちゃんと」「しっかり」など)を避ける
・期待する水準・成果物の「完成イメージ」を見せる
・「なぜそれが重要なのか」を繰り返し伝える
具体的に、なにを、どこまでかが明確でないと、人は動けません。
「感情」より「仕組み」で伝える
忙しくなってくると、社長の伝え方が感情的になってしまうことがあります。
・「なんでこんなことも分からないんだ」
・「前にも言ったよね?」
・「ちゃんとやってよ!」
これでは、社員は委縮するか、心を閉ざすだけで、悪循環に入ってしまいます。
(改善ポイント)
・伝えたいことを「3つ以内」に絞る
・メールやチャットで「見返せる伝達」にする
・日報・週報など「伝達の定例化」をつくる
感情ではなく、「伝える構造」を整えることが行動変容の近道です。
のびしろ経営の支援事例
G社では「社員が自分で考えて動けない」という悩みが続いていました。
聞くと、
・指示が「口頭で都度」行われていた
・社員は「どこまでがOKか」が不明
・叱責が感情的になっていた
そこで、
・「伝達のフォーマット」をつくった(目的・期限・成果物)
・指示と報告を毎週面談で実施をルール化
・フィードバックを必ず行うように
結果、社員の自走が進み、社長が現場に口を出す頻度は減りました。
「伝える力」は経営スキル
人を動かすのは、「人柄」でも「カリスマ性」でもありません。
日々の伝え方の積み重ねが、組織の行動を変えます。
のびしろ経営では、社員が動き出す「社長の伝え方改革」や、指示の仕組み化、現場とのルールづくりまで伴走支援しています。