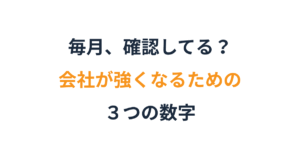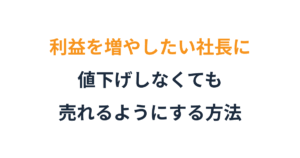育たない原因は「社員」ではなく、「仕組み」かもしれない

株式会社のびしろ経営
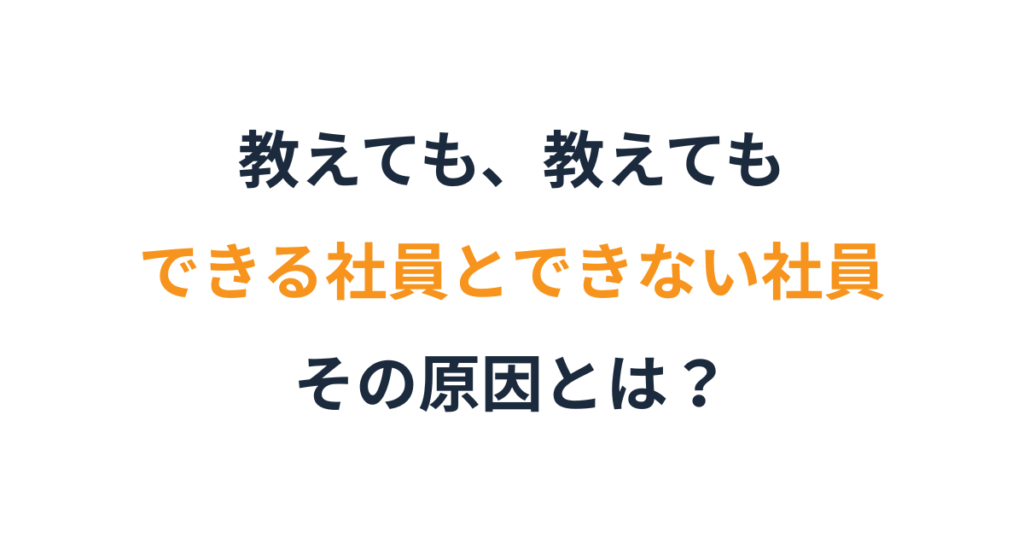
「何度いってもできるようにならない」
「教えても、定着しない」
「結局、育たないのは本人の問題なのでは?」
このように感じたことのある経営者は多いと思います。
ですが、実はそこに落とし穴があります。
「育たない」のは、人ではなく、仕組みに原因があることが多いのです。
今回は、社員が育つ組織と育たない組織の違いを「仕組み」という視点で解説します。
「人が育たない」会社に共通する3つの構造
①教える内容が「属人的」でバラバラ
現場任せで、「見て覚えろ」方式になっている会社は多く、
誰が教えるかによって、内容や質が異なり、学ぶ側にとっての「基準」が無い状態です。
②「教えたつもり」で終わっている
教えること = 伝えること、ではありません
伝えたあとに「できるようになったか?」を確認するプロセスがなければ、知識は身につかず、行動に反映されません。
③成長が評価・報酬に反映されない
人は「評価されない行動」を継続しません。
努力しても、正当に評価されなければ、やる気も育ちません。
育つ組織にある「3つの仕組み」
①教える内容が明確になっている
・業務のチェックリスト
・1~2ヶ月で学ぶべき項目
・初級・中級・上級のステップ
これらが明確にあることで、教える側、学ぶ側のズレがなくなります。
②育成のサイクルがある
・OJT(オン・ザ・ジョブトレーニング)
・定期的な振り返り面談
・フィードバックと再指導の仕組み
「1回教えたら終わり」ではなく、定点的に見直すサイクルがあることが成長を促します。
③成長と評価がつながっている
・スキルシートでできることを見える化
・給与や役割と連動させる
・小さな成長もきちんと承認する文化
これにより、「もっとできるようになりたい」という内発的動機づけが生まれます。
のびしろ経営の支援事例
B社では、「新人が定着しない」「教えても動けない」という課題が続いていました。
ヒアリングの結果、
・先輩によって教える内容がバラバラ
・何ができればOKかが不明確
・評価は「上司の印象」だけで決まっていた
という状態であることが判明。
そこで、
・業務ごとのスキルマップを作成
・教育の手順書を標準化
・「できた」を見える化した育成表を導入
その結果、新人が1か月で「自分がなにを覚えればいいか」を把握し、
教える側も、「何を見て判断すればいいか」が統一され、定着率が改善しました。
「人の問題」は「仕組みの問題」
社員が育たないとき、「人が悪い」と片付けるのは簡単です。
でも、長い目で見れば、それは「組織の成長を止める考え方」です。
仕組みを整えれば、人は想像以上に育ちます。
そして、その「育てる仕組み」こそが、小さな会社の「のびしろ」なのです。
のびしろ経営では教育や、スキル評価精度、育成PDCA導入支援など、人が育つ仕組みづくりを現場と一緒に進めています。