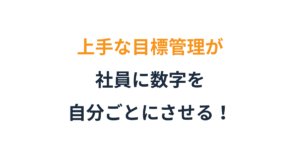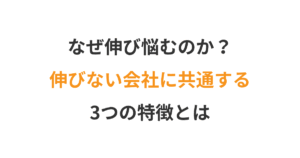給料の決め方に迷う社長へ。評価と報酬の設計の基本

株式会社のびしろ経営
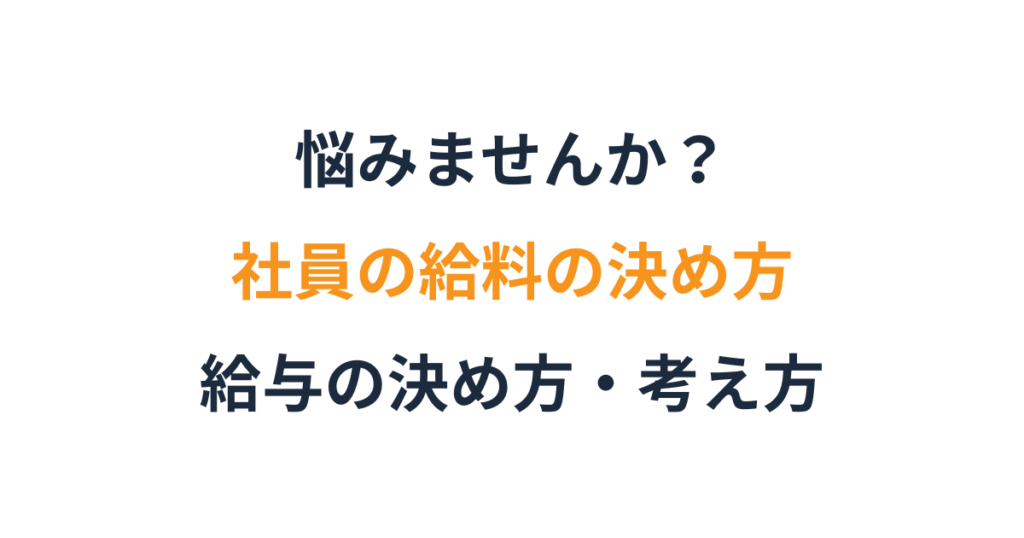
「頑張っている社員に、どう報いたらいいのか…」
「給与を上げたいけど、どの基準で上げれば納得感があるのか」
「社員から ”評価の基準がわからない” と言われた」
中小企業の社長にとって、「給料の決め方」は永遠の悩みとも言えるテーマです。
ですが、評価と報酬の関係をシンプルに整理するだけで、社員の納得感と会社の安定経営は両立できます。
今回は、小さな会社でもすぐに実践できる評価と報酬の設計の基本をお伝えします。
「感覚評価」が社員の不満を生む
「なんとなく上げる」「前年と同じ昇給額にする」
こうした ”感覚の評価” は、以下のような問題を引き起こします。
・頑張った人が報われず、不公平感が残る
・社員が何を目指せば昇給できるのかが不明確
・評価と給料が結びついていないため、動機にならない
給与は「成果の報酬」である以上、評価の仕組みと連動していないと、信頼を失います。
報酬設計で大切なのは「3つのバランス」
①成果と報酬のバランス
→ 数字目標・実行内容・会社への貢献度などに対して、どの程度の報酬を与えるかを明示する。
②継続性とのバランス
→ 上げすぎて来年以降の人件費を圧迫しないよう、業績・財務とのバランスを取る。
③公平性のバランス
→ 同じ職種・役割で、明らかな差がつくような昇給・賞与であれば、その理由を明確に示す必要があります。
評価制度をシンプルに設計する3ステップ
ステップ① 評価軸を3つ程度に絞る
例えば
・業務スキル(例:正確さ・スピード・仕事のやり方)
・貢献姿勢(例:協力・提案・社内の雰囲気づくり)
・成果(例:売上・改善提案数・原価削減)
数字で出ない職種にも評価できるよう、定性+定量のバランスが大切です。
ステップ② 「昇給条件」を見える化する
・スキル評価が3段階上がったら昇給
・年間売上目標を達成 + 貢献度が高ければ手当アップ
など、「どうすれば上がるか」を事前に見せておくことで、社員の納得感と目標意識が高まります。
ステップ③ 面談やフィードバックの場を持つ
評価は伝えてこそ意味があります。
・四半期ごとの1on1
・年1回の振り返りと目標設定面談
などを通じて、「評価 → 納得 → 次の行動」につなげる仕組みをつくりましょう。
よくある誤解「報酬を上げないと辞める」
たしかに報酬は大切です。
ですが、金額以上に大事なのは「納得感と未来の見通し」です。
・「自分の頑張りは見てもらえている」
・「あと〇ヶ月で昇給のチャンスがある」
・「評価は公平にされている」
このような状態をつくるだけで、社員は今よりも前向きに働けるようになります。
報酬は「感謝」ではなく「戦略」
報酬は勘定で決めるものではなく、
会社の経営戦略と社員の成長をつなぐ「仕組み」として設計するものです。
のびしろ経営では、社員数が少ない企業でも社員を評価しお給料を決める方法をサポートしています。
「感覚」から「仕組み」へ。
社員の力を最大化する報酬設計を、今こそ見直してみませんか?