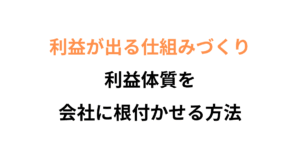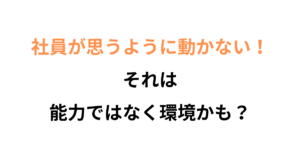価格は「決めるもの」ではなく、「設計するもの」

株式会社のびしろ経営
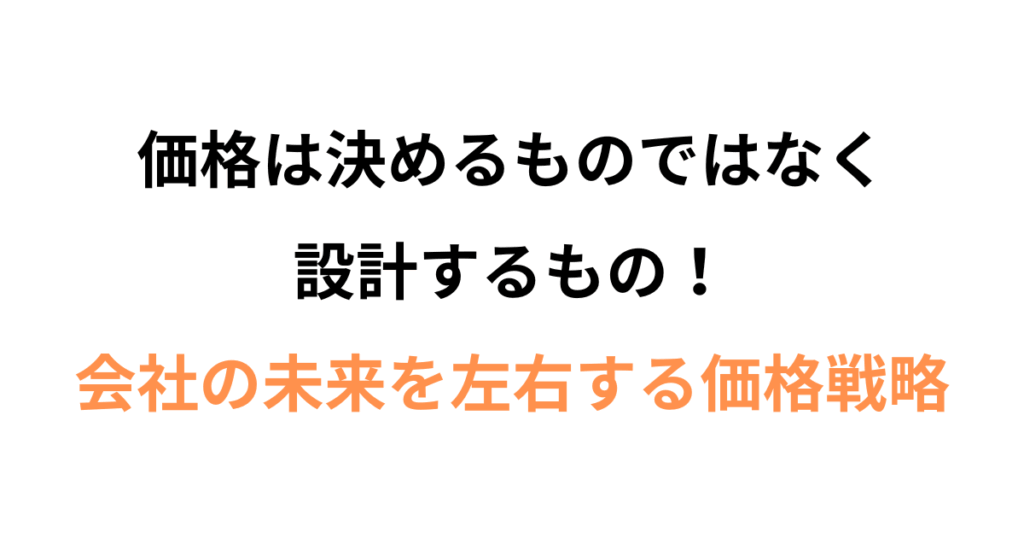
「この商品、いくらで売ればいいんだろう?」
「とりあえず、原価に利益をのせて決めよう」
そんな風に「なんとなく」価格を決めていませんか?
価格は、商品やサービスの価値をあらわす大切なメッセージであり、会社の利益を左右する戦略の根幹です。
だからこそ、価格は「感覚」ではなく、「設計」して決めるものです。
今回は、社長の頭の中にある「価格=値段」というイメージを、「価格=仕組み」として再設計するための視点をお伝えします。
「原価+利益」で価格を決めていませんか?
中小企業でよく見られる価格設定は、「原価に●%の利益をのせる」という方法です。
たしかに、シンプルで分かりやすいですが、このやり方には落とし穴があります。
・「利益」は確保できても、「価値」が反映されていない
・競合との比較で価格に自信が持てず、値引きに走ってしまう
・市場や顧客の変化に対応しづらい
つまり「守りの価格」になりがちなのです
価格は「4つの視点」で設計する
価格設計には、以下の4つの要素を整理する必要があります。
①コスト(原価)
当然ながら、最低限「損しない」価格は、原価から把握する必要があります。
②顧客価値(相手にとってのメリット)
・時間の節約になる
・安心を提供できる
・自社でやるより高い効果が出る
など、「お金以外の価値」をどう評価してもらうか?がポイントです。
③競合との位置づけ
・自社は価格で勝負するのか?
・それとも品質やサービスで勝負するのか?
明確にすることで、価格に「根拠」が生まれます。
④収益構造(ビジネスモデル)
・1回の販売で利益を出すのか?
・継続的な関係で収益を得るのか?
「価格×数量」だけでなく、「リピート性」や「契約期間」まで含めて設計するのが理想です。
価格設計を間違えると、会社の未来が削られる
例えば、安易に価格を下げれば、
・粗利が減って人件費が払えなくなる
・開発や教育にお金をかけられなくなる
・いいスタッフが定着しなくなる
つまり、短期的な売上を取る代わりに、会社の「のびしろ」を削っていることになります。
価格は「伝え方」で変わる
価格は金額そのものではなく、「その価格に納得してもらえるかどうか」がすべてです。
・提案書のつくり方
・事前説明のトーン
・料金プランの見せ方
こうした伝え方を磨くことで、同じ金額でも「高い」ではなく、「納得できる」と思ってもらえるようになります。
価格は「意思」であり、「設計図」
「この価格で売りたい」ではなく、
「この価格で売れる仕組みをどう設計するか?」が社長の腕の見せどころです。
価格は、会社のビジョンと利益を両立させる最強の戦略ツール。
のびしろ経営では、価値・構造・見せ方まで含めた「利益の残る価格設計」を伴走支援しています。
次の値付けは、偶然ではなく「設計」して決めませんか?